PR
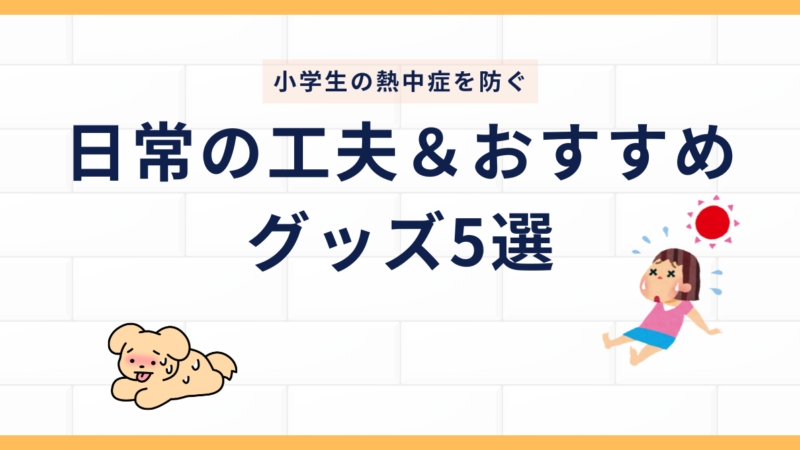
夏になると心配になるのが、子どもの熱中症。
特に小学生は通学や外遊び、体育や習い事など、屋外で過ごす時間も多く、大人よりも熱中症にかかりやすいとされています。
実は私自身、長女が小学1年生の頃に、地元の公園で開催されていた夏のイベントに参加した際、長女が熱中症で倒れてしまった経験があります。
幸い、イベント会場に看護師さんが待機してくださっていて、すぐにエアコンの効いた室内で休ませることができ、大事には至りませんでした。
でも、もしあの場に看護師さんがいなかったら、すぐに涼しい場所がなかったら…と今でもゾッとします。
その時は、完全に私の準備不足でした。
「現地で飲み物を買えばいい」と、水筒すら持たせず、クールネックなどの暑さ対策グッズも一切なし。「大丈夫だろう」と安易に考えていた自分の甘さを、今でも深く後悔しています。
こうした経験をきっかけに、「熱中症対策は親の準備が大切」と強く感じるようになりました。
この記事では、同じような思いをする親子を一人でも減らしたいという思いから、日常でできる熱中症予防の工夫や、実際に役立ったおすすめグッズを紹介していきます。
1. 登下校時は「帽子+水筒」が鉄則!

真夏の登下校は、それだけで立派な“運動”です。
炎天下をランドセルを背負って歩く小学生にとっては、通学時間だけでも熱中症のリスクが高まります。
そこで欠かせないのが、通気性の良い帽子と、冷たい飲み物が入った水筒です。
とくに低学年のうちは、まだ自己判断が難しいため、「帽子をかぶる習慣」「のどが渇く前に水を飲む習慣」をしっかりつけてあげたいところ。
我が家では、暑い日は「5回は水筒飲んでね」と朝に声をかけています。
帽子は、あご紐つきで飛ばされにくいタイプがおすすめです。汗をかいても蒸れにくい、メッシュやUVカット素材ならより安心。
「暑さに慣れているから大丈夫」と思わずに、まずは親が“装備”を整えてあげることが大切です。
2. 朝ごはんは抜かない|水分・塩分が朝食で決まる

「朝は食欲がなくて…」「時間がなくてバタバタで…」
そんな声もよく聞きますが、朝ごはん抜き=熱中症リスクUPと考えてください。
子どもは寝ている間に汗をかいて水分を失っています。朝食を通して、水分・塩分・エネルギーをしっかり補うことで、暑さに負けない体を作ることができます。
おすすめは、味噌汁+ごはん+果物などのシンプルな組み合わせ。
我が家では夏になると、朝食にスイカやキウイなどの水分の多い果物を積極的に取り入れています。
パン派のご家庭なら、チーズトーストや具だくさんスープなどで塩分を補うのも◎。
「朝にちゃんと食べる」
たったそれだけで、子どもが夏バテしにくくなります。
3. 学校に行く前に「今日の暑さ指数」をチェック
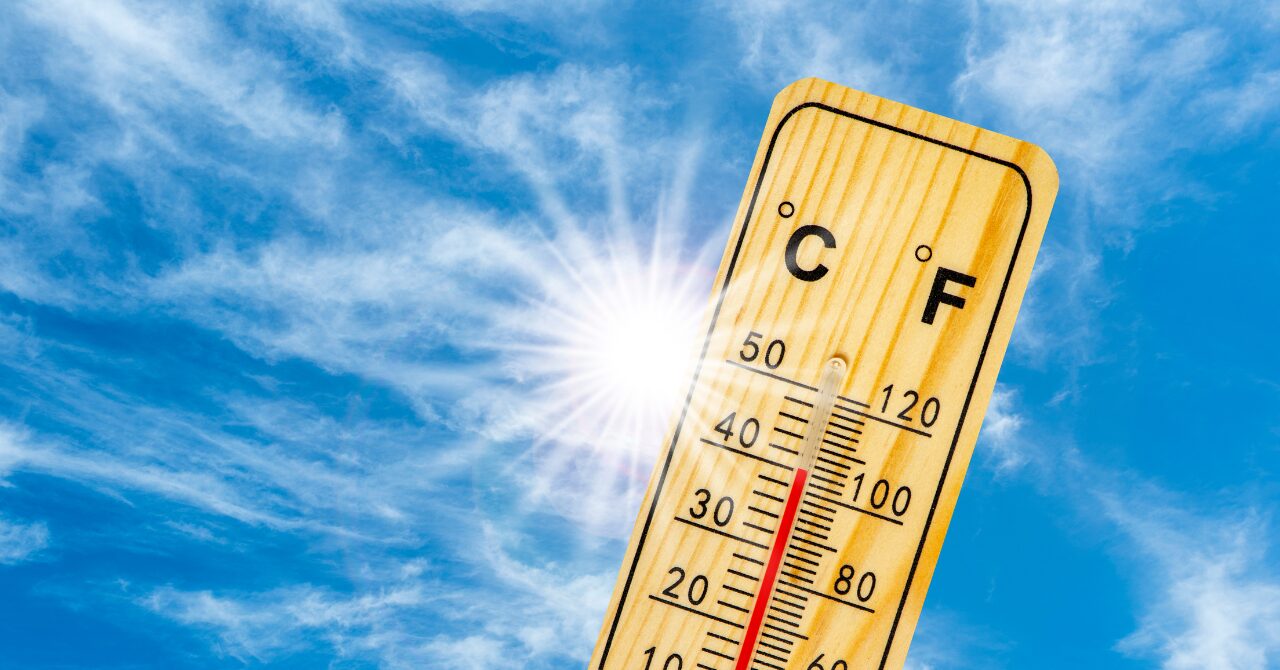
朝、「今日ってどのくらい暑くなるんだろう?」と思ったことありませんか?
そんなときに便利なのが、暑さ指数(WBGT)の確認です。
これは単なる気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面からの熱)などを考慮して、熱中症のリスクを数値化したもの。
気象庁や環境省のサイト、アプリでも無料で確認できます。
たとえば…
- 警戒:外遊びや体育は要注意
- 厳重警戒:できれば涼しい屋内で過ごす
- 危険:運動禁止レベル。外出も控える
我が家では、夏休み中の外遊びはこの指数を目安に「今日は朝のうちだけ公園」「今日は家の中で遊ぼう」など、子どもと相談して決めています。
【おすすめアプリ】
▶︎ 熱中症警戒 – 気象庁 –
「暑いけど…大丈夫かな?」と悩んだときの目安に、ぜひチェックしてみてください。
4. お風呂と睡眠がカギ!体調を整えておく

熱中症は、外の暑さだけが原因ではありません。
体の中のコンディションが整っていないと、わずかな暑さでも症状が出やすくなります。
その体調を左右するのが、「お風呂」と「睡眠」。
夏はシャワーだけで済ませてしまいがちですが、できればぬるめのお湯にしっかり浸かるのがおすすめです。
血流がよくなり、体温調節機能がスムーズになります。
また、夜ふかしや寝不足が続くと、体力が落ちて熱中症になりやすくなります。
エアコンや扇風機をうまく使って、しっかり眠れる環境を整えることも、立派な熱中症対策です。
うちでは、寝る前に部屋を一度冷やしておいて、子どもが寝た後に少し温度を上げたり、タイマー設定で自然に切れるようにしています。
朝の目覚めもスッキリするのでおすすめです。
5. 「なんか変?」と思ったらすぐ休ませる

熱中症は、突然ひどくなるわけではありません。
最初は「ちょっと疲れたかな?」「なんか元気ないかも?」という、小さなサインから始まります。
でもその小さな変化に気づけるかどうかで、その後の体調は大きく変わります。
たとえば、こんな様子が見られたら要注意
- 顔が赤く、汗をたくさんかいている(or 全然かいていない)
- 元気がない、ぼーっとしている
- 頭が痛い、お腹が痛い、吐き気があると言う
こうしたサインに気づいたら、すぐに涼しい場所で休ませ、水分補給をさせることが第一。
可能なら首・脇・足の付け根を冷やして体温を下げると、回復が早まります。
あのとき娘が倒れた場面を思い出すと、少しずつ顔色が悪くなり、目がトロンとしてきていたのに「疲れただけかな」と軽く考えてしまっていた自分がいました。
子どものちょっとした「違和感」に気づけるのは、やっぱり一番そばにいる親です。
「あれ?」と思ったら、すぐ休ませてあげてください。
環境省の熱中症予防資料でも、
「顔が赤く、ひどく汗をかいている場合には、深部体温がかなり上昇していると推察できるので、涼しい環境下で十分な休息を与えましょう」
出典:環境省熱中症予防情報サイト
とされています。
つまり、親が少しでも「おかしいな」と感じたときにすぐに対応することが、重症化を防ぐカギになります。
熱中症対策におすすめの便利グッズ5選

ここからは、実際に我が家でも使っている・使ってよかったと感じた熱中症対策グッズをご紹介します。
どれも「もっと早く用意しておけばよかった…」と思ったものばかりです。
通学・外遊び・習い事など、いろんなシーンで使えるものを厳選しています。
① クールネック(保冷材つきタイプ)
首元を冷やすだけで、体全体の熱を効率よく下げてくれる便利アイテム。
登下校・外遊び・スポーツ・イベントなど、どんなシーンでも使いやすく、子どもが自分で着脱できるのも嬉しいポイント。
我が家では、イベント参加時にこのクールネックをしていたら「前より全然元気に過ごせた」と娘が言っていました。
冷凍庫で凍らせて持たせるだけなので準備も簡単。保冷時間が長いタイプを選ぶのがコツです。
こちらもおすすめ
② 子ども向け軽量ステンレス水筒(ワンタッチ開閉)
水筒は毎日の登下校に欠かせないもの。
暑い日でも冷たい飲み物が飲めるように、真空断熱タイプの軽量ボトルがおすすめです。
ポイントは以下の3つ
- 500ml前後のサイズ感(重すぎず足りすぎず)
- ワンタッチで開くふた(子どもでも使いやすい)
- 直飲みタイプ or コップタイプの選択(年齢に応じて)
③ 冷感タオル・ミストスプレー
外遊びやスポーツのあとにさっと使える冷感タオルやミストスプレーも、夏の必需品です。
濡らして振るだけで冷たくなるタオルは、ランドセルのポケットに入れておいてもOK。
ミストスプレーは、衣類に吹きかけると一気に涼しくなります。
「遊びに夢中になる前にシュッと一吹き」するだけでも、体温の上がりすぎを防げます。
▶︎ おすすめ商品リンク
④携帯型熱中症チェッカー(親向け)
公園、野外イベント、スポーツ観戦など、外出先での「暑さの見える化」ができる便利グッズ。
温度や湿度、WBGT値(暑さ指数)を測ってくれるので、今日はどのくらい警戒すべきか?がすぐにわかります。
体感だけでは判断しにくいときも、こうした道具があると行動の目安になります。
「今日はちょっとやめておこうか」という判断をしやすくなるので、親御さんにこそ持っていてほしいアイテムです。
⑤ベースボールキャップ(UVカット・メッシュ素材)
通気性に優れた帽子は、夏の外出時のマストアイテム。
特にUVカット+メッシュ素材のキャップは、汗をかいても蒸れにくく、快適に過ごせます。
我が家では、子どもが「お気に入りの帽子」だと自分から進んでかぶってくれるようになりました。
お気に入りの色や柄で選ぶのも、立派な熱中症対策です。
以上の5つのアイテムは、どれも「いざという時」に備えるというより、日々の習慣に取り入れるべき夏の標準装備だと感じています。
準備しておくだけで、親の安心感もぐっと変わりますよ。
まとめ:熱中症対策は「親の準備」で8割決まる!

子どもは、大人が思っている以上に暑さの変化に敏感で、かつ自己判断が難しい存在です。
とくに小学生は、夢中で遊んだり頑張って登校しているうちに、体の限界に気づけず、気づいたときには症状が出てしまっている――そんなケースが本当に多いと感じます。
私自身、長女が熱中症で倒れてしまった経験をしてから、「大丈夫だろう」という油断が一番危険なんだと痛感しました。
水筒・帽子・クールグッズ・体調管理――
どれも「当たり前」のようで、ひとつでも欠けるとリスクは一気に高まります。
でも逆に言えば、日常のちょっとした工夫と便利なグッズの準備があれば、熱中症はかなり防げるということでもあります。
今年の夏は、万全の準備で「安心して笑顔で外遊びや登下校ができる毎日」を目指していきましょう。
子どもたちの安全は、親の“ちょっとしたひと手間”から守ることができます。